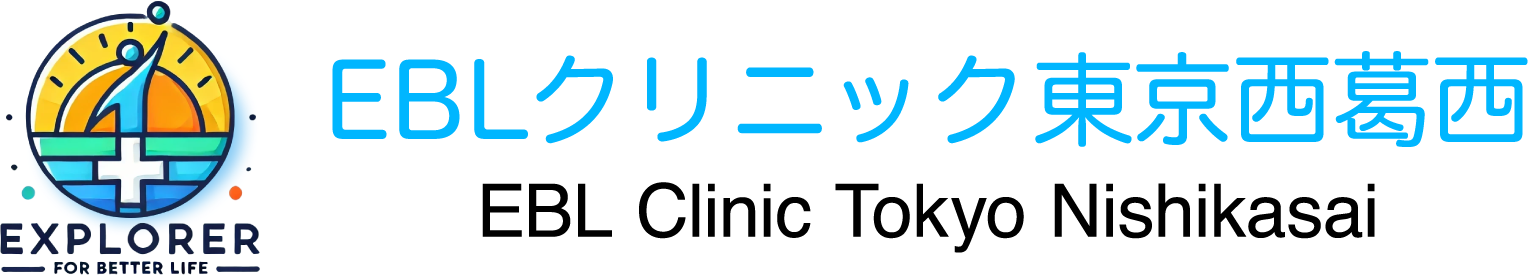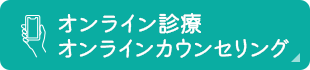精神科で使用する薬のイメージは?
 当院では、治療における薬の使用は最小限にするように努めています。また、薬物療法が必要な場合では、患者様の体調や症状や、予想される副作用についても考慮したうえで、処方を行います。以下は精神科で使用される処方薬の一例です。
当院では、治療における薬の使用は最小限にするように努めています。また、薬物療法が必要な場合では、患者様の体調や症状や、予想される副作用についても考慮したうえで、処方を行います。以下は精神科で使用される処方薬の一例です。
※薬品名は「一般名(商品名)」で表記しています。
抗うつ薬
抗うつ薬は、うつ病や抑うつ状態の改善、気分や意欲の回復などで処方します。
エスシタロプラム(レクサプロ)
エスシタロプラムとは、脳内物質のセロトニンを増やす働きをするSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)の一種です。エスシタロプラムは、うつ病のほかに、パニック障害や一部の不安障害にも処方することがあります。効果を確認しながら段階的に投与量を増やしたり、減らしたりします。
デュロキセチン(サインバルタ)
デュロキセチンとは、脳内物質のセロトニンとノルアドレナリンを増やす働きをするSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)の一種です。抑うつ状態の改善と、意欲の向上を図ります。効果を確認しながら段階的に投与量を増やしたり、減らしたりします。
ボルチオキセチン(トリンテリックス)
ボルチオキセチンとは、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)の一種です。従来のSSRIの作用に加えて、ノルアドレナリン、ドーパミン、アセチルコリン、ヒスタミンの調整に働くため、不安症状に効果が期待できます。処方を開始してすぐに吐き気や下痢といった副作用が現れることがありますが、多くの場合、1週間程度で落ち着きます。
睡眠薬
睡眠薬は、不眠を改善する目的で処方します。薬が作用する時間の長さによって、超短時間型、短時間型、中時間型、長時間型に分かれます。近年では、依存度が低く、自然な眠りが得られる睡眠薬が開発の主流となっています。
レンボレキサント(デエビゴ)
レンボレキサントとは、オレキシンという覚醒を維持する脳内物質の働きを抑える方法で、睡眠を促す睡眠薬(オレキシン受容体拮抗薬)で比較的新しい薬です。入眠、睡眠の維持、熟眠障害などに効果が高く、依存性がないという特徴があります。しかし、効果が得られやすい人と、効果が得られにくい人がいます。
ラメルテオン(ロゼレム)
ラメルテオンとは、睡眠のリズムを整え、自然な眠りを促す睡眠薬です。軽度の不眠症に効果が期待できます。就寝前に服用します。副作用は少ないとされていますが、稀に眠気や倦怠感が起こるとされています。なお、肝機能障害のある方には使用できません。
マイスリー(ゾルピデム)
マイスリーとは、非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬で、ふらつきが少なく、依存性の低い睡眠薬です。服用後は比較的短時間で効果が現れ、作用時間は短いため、翌日に眠気が残りづらいという特徴があります。
ブロチゾラム(レンドルミン)
ブロチゾラムとは、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬です。効果が短時間で現れるため、入眠障害や中途覚醒タイプの睡眠障害に適した薬です。効果は高いですが、依存のリスクがあるため、使用には注意が必要です。睡眠導入剤として処方日数の制限が規定されている薬です。
抗不安薬
抗不安薬は、日常生活に支障が出るほどの強い不安や緊張を和らげる目的で処方します。精神安定剤とも呼びます。効果の強さ(弱・中・強)や持続時間(短・中・長)で分けられ、症状に合わせて適したものを処方します。
ロラゼパム(ワイパックス)
ロラゼパムとは、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の一種です。効果は強く、持続時間は中程度です。15~30分で効果が現れ、6時間程度効果が持続するため、頓服としても使用することが可能です。しかし、依存には注意が必要なため、様子を見ながら用量を調整していきます。
ロフラゼプ酸エチル(メイラックス)
ロフラゼプ酸エチルとは、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の一種で、効果は中程度、持続時間は24時間以上と長いです。そのため、就寝前に服用するだけで、翌日も1日中効果が持続します。依存性は少ないですが、日中にやや眠気を感じることがあります。
エチゾラム(デパス)
エチゾラムとは、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の一種です。エチゾラムは効果が強く、不安・うつ症状だけでなく、睡眠障害や筋収縮性頭痛、腰痛など幅広い症状に使用されますが、乱用や依存に繋がりやすいため服用上のリスクも多く、注意点が多い薬です。エチゾラムは脳の働きを落ち着ける抗不安薬として日本で最も処方されている薬です。なお、エチゾラムは2016年10月より向精神薬に指定され、厚生労働省による処方制限の対象となりました。
抗不安薬の依存性が心配な方へ
ベンゾジアゼピン系抗不安薬
ベンゾジアゼピンとは、脳内のベンゾジアゼピン受容体に働きかけ、脳の興奮を抑える神経伝達物質のGABAの働きを高める物質です。ベンゾジアゼピンは抗不安薬や睡眠薬として用いられることが多く、中でも抗不安薬としては即効性が高く、15~30分程度の短時間で効果が現れます。その他にも、抗不安作用、抗うつ作用、筋弛緩作用、催眠作用、抗けいれん作用などの多くの薬効があり、幅広い症状に使用されますが、薬に対する依存性が高く、急に服用を中止すると様々な副作用が出るため、短期間での使用が望ましい薬です。
セロトニン1A部分作動薬
セロトニン1A部分作動薬とは、1~7まであるセロトニンの受容体のうち1Aに分類される受容体に働き、セロトニンの過剰活動を抑えることで効果を現す抗不安薬です。ベンゾジアゼピン系の抗不安薬のように依存性はありませんが、効果がやや弱いため、使用する場面を選ぶ薬です。
抗精神病薬
抗精神病薬とは、統合失調症の治療薬です。抗精神病薬は、幻覚や妄想などの症状(陽性症状)に効果がある定型抗精神病薬と、感情の平板化(外部からの刺激に対して、喜怒哀楽などの感情が起こりにくくなる)などの症状(陰性症状)に効果がある非定型抗精神病薬の2つに分けられます。
アリピプラゾール(エビリファイ)
アリピプラゾールとは、ドーパミンという脳内の神経伝達物質の働きを調整することで、症状を調整する非定型抗精神病薬で、躁うつ病(双極性障害)の治療にも用いられることがある抗精神病薬です。比較的副作用が少ない薬ですが、手足の震えやけいれん、めまい、頭痛といった症状が現れることがあります。
リスペリドン(リスパダール)
リスペリドンとは、非定型抗精神病薬の一種で、セロトニンとドーパミンの双方を調整することで、症状を調整するセロトニン・ドーパミン拮抗薬です。リスペリドンは統合失調症の治療だけでなく自閉症スペクトラム症の治療に使用されることもあります。副作用の現れ方には個人差があるため、医師と相談しながら服用を決めます。
オランザピン(ジプレキサ)
オランザピンとは、非定型抗精神病薬の一種で、多元受容体標的化抗精神病薬(MARTA)に分類されます。オランザピンは統合失調症だけでなく、躁うつ病(双極性障害)やうつ病の治療にも用いられます。特に気分の波を抑える効果が高く、こわばりや震えなどの副作用が出にくいという特徴があります。しかし、体重増加や血糖値上昇効果があるため、糖尿病の方には使用ができません(禁忌)。
ルラシドン(ラツーダ)
ルラシドンとは、非定型抗精神病薬の一種で、幻覚や妄想、認知機能の改善や不安や落ち込みなどの情動を少しずつ改善させる効果が期待されます。ルラシドンは、統合失調症のほかにも、躁うつ病(双極性障害)やうつ状態に対しても使用が検討されます。
気分安定薬
気分安定薬とは、躁うつ病(双極性障害)の両極(躁状態・うつ状態)の症状を改善し、予防する効果がある薬です。
炭酸リチウム(リーマス)
炭酸リチウムとは、気分安定剤の一種で躁状態やうつ状態に有効とされており、中枢神経に作用して、気分の高揚やそれによる行動を抑える効果があります。特に躁状態への効果が高く、それに比べてうつ状態への効果は少し弱いとされています。副作用が多く、めまいや頭痛、眠気、吐き気、嘔吐、下痢などが現れることがあります。また、非ステロイド性抗炎症薬(NASIDs)との併用に注意が必要で、血中濃度を計測することが求められます。
バルプロ酸ナトリウム(デパケン)
バルプロ酸ナトリウムとは、気分安定剤の一種で躁状態に効果が高いとされています。バルプロ酸ナトリウムは躁うつ病(双極性障害)のほかにも、てんかんや片頭痛などの治療に使用します。肝障害や急性膵炎、間質性肺炎、生殖機能に影響が出ることもあるため注意が必要です。
妊娠を考えられている女性の方へ
バルプロ酸ナトリウムは、生殖機能に影響を及ぼす副作用があり、月経不順や無月経、稀に他嚢胞性卵巣症候群を起こすことがあるため、特に妊娠を希望している女性には注意が必要な薬です。他嚢胞性卵巣症候群は、卵巣の中で成長が途中で止まって嚢胞の形になった乱視が溜まってしまう病気で、不妊症を引き起こしたり、胎児の奇形を引き起こす可能性が高くなります。さらにバルプロ酸ナトリウムは胎児の認知形成にも影響を与えると考えられています。妊娠を希望される時期には、バルプロ酸ナトリウムの使用を中止し、他の薬を使用しますが、どうしてもバルプロ酸ナトリウムでなければ効果が得られない場合は、分量を抑えて処方します。
カルバマゼピン(テグレトール)
カルバマゼピンとは、気分安定剤の一種で、脳の興奮に関係する神経に作用して、脳の興奮を抑える効果があります。もともとはてんかん発作や三叉神経痛の治療薬として承認されていた薬でしたが、その後に躁うつ病(双極性障害)の躁状態にも効果があることがわかり、躁うつ病(双極性障害)の治療薬としても承認されました。カルバマゼピンは飲み合わせが難しい薬で、薬だけでなくグレープフルーツジュースやアルコールなどとの併用に注意が必要です。また、眠気やめまい、ふらつき、倦怠感、運動失調、脱力感、発疹などが現れることがあります。特に発疹があらわれた場合には、お早めにご相談ください。
ラモトリギン(ラミクタール)
ラモトリギンとは、気分安定剤の一種で、てんかん発作や躁うつ病(双極性障害)の治療に用います。ラモトリギンを自殺願望のある方に投与すると、不安感が大きくなることがあるため、重いうつ状態にある方への投与は注意が必要です。また、副作用として皮膚障害を起こしやすい傾向があるため、投与開始から2ヵ月程度は慎重に観察する必要があります。
認知症治療
ドネペジル(アリセプト)
ドネペジルとは、アセチルコリンという脳内物質の減少を抑制することで、アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の進行を遅らせる薬です。根本治療ではなく、進行を抑制する薬であるため、併せて介護対策などを行うことが必要です。
メマンチン(メマリー)
メマンチンとは、中程度から高程度のアルツハイマー型認知症の進行を遅らせる薬で、認知症により過剰になったグルタミン酸を抑える働きがあります。副作用として、服用初期にめまいが現れることがあります。
漢方薬
不眠
酸棗仁湯(サンソウニントウ)
サンソウニントウとは、神経症や自律神経失調症などによる不眠に用いられる漢方薬です。主薬はサンソウニンで、気を鎮める働きがあるブクリョウなどが加わっており、心身の疲労によって体力が低下している方に向いています。睡眠のリズムが乱れてしまい、熟睡ができなかったり、寝ようとしても眠れないような不眠の方に適しています。
黄連解毒湯(オウレンゲドクトウ)
オウレンゲドクトウとは、オウゴン、オウレン、サンシシ、オウバクを配合した漢方薬で、不眠やイライラなどの精神神経症状や、めまい、動悸、湿疹、皮膚炎などの皮膚症状、胃炎などの胃腸症状など様々な症状に効果があります。また、女性ホルモンの変動によって現れる精神神経的な症状にも有効です。体力が中程度以上で、赤ら顔でのぼせ気味の方に向いています。
加味帰脾湯(カミキヒトウ)
カミキヒトウとは、ニンジン、トウキ、サンシシ、タイソウ、ショウキョウなどを成分とした漢方薬で、虚弱体質や、貧血があり顔色が悪い方に向いています。胃腸の働きを改善し、不足する身体の栄養を増やすことで、気が高ぶって眠りが浅くなるような不眠を改善します。イライラなどの精神神経症状にも効果があります。
抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ)
ヨクカンサンカチンピハンゲとは、ソウジュツ、ブクリョウ、トウキ、センキョウなどにチンピとハンゲを加えた漢方薬です。身体の栄養不足を補い、肝臓の働きや自律神経の機能を改善します。体力が中程度でやや胃腸が弱い方に向いています。また、女性ホルモンの変動による心身症状や子どもの夜泣きにも有効です。
抑肝散(ヨクカンサン)
ヨクカンサンとは、ソウジュツ、ブクリョウ、トウキ、センキョウなどを主成分とする漢方薬です。体力が中程度の方に向いており、イライラや興奮を抑え、神経症や不眠症、女性ホルモンの変動に伴う心身症状などに効果があります。
不安、パニック
半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)
ハンゲコウボクトウとは、ハンゲ、コウボク、ブクリョウ、ソヨウ、ショウキョウを成分とした漢方薬です。体力が中程度で精神的な不調によって喉が塞がる感じや、胃腸に影響が出ている方に向いています。
加味帰脾湯(カミキヒトウ)
カミキヒトウとは、ニンジン、トウキ、サンシシ、タイソウ、ショウキョウなどを成分とした漢方薬で、虚弱体質や、貧血があり顔色が悪い方に向いています。オキシトシンの分泌を促進し、パニック発作や不安、強いストレスを低減する効果があります。
PMS、PMDD
加味逍遙散(カミショウヨウサン)
カミショウヨウサンとは、トウキ、ビャクジュツ、サイコ、ショウキョウなどにサンシシとボタンピを加えた漢方薬です。体力が中程度以下の方に向いています。婦人科症状に用いられることが多く、婦人科三大漢方薬の1つに数えられています。男性のイライラや抑うつ症状にも有効とされています。
当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)
トウキシャクヤクサンとは、トウキ、シャクヤク、ソウジュツ、タクシャなどを配合した漢方薬で、不足した身体の栄養を補って血のめぐりを改善し、体を温める効果があります。虚弱体質でやせ型、貧血気味の方に向いています。婦人科三大漢方薬の1つで、月経痛や月経不順、更年期障害、貧血、疲労感、めまいなどの症状に効果的です。
桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)
ケイシブクリョウガンとは、ケイシ、ブクリョウ、トウニン、シャクヤク、ボタンピを配合した漢方薬です。比較的体力がある方や赤ら顔気味の方に向いています。血行を改善し、のぼせや冷えを解消することで、女性ホルモンの変動に伴う心身症状や頭痛、めまい、肩こり、足の冷えなどを改善します。
女神散(ニョシンサン)
ニョシンサンとは、コウブシ、センキョウ、ソウジュツ、トウキ、オウゴン、ケイヒなどを配合した漢方薬です。体力が中程度以上の方に向いています。血行不良によって、のぼせやめまい、肩こり、精神の不安定などを起こしている女性に用いられることが多く、長期的に服用することで女性ホルモンの変動に伴う心身症状に効果があります。
桃核承気湯(トウカクジョウキトウ)
トウカクジョウキトウとは、トウニン、ケイヒ、ダイオウ、カンゾウ、無水ボウショウを配合した漢方薬です。体力が中程度以上で便秘がちの方に向いています。月経前や月経中の心身症状を改善する効果があり、特にイライラや不安を鎮めます。また、ホルモンバランスを正常に整える効果もあります。