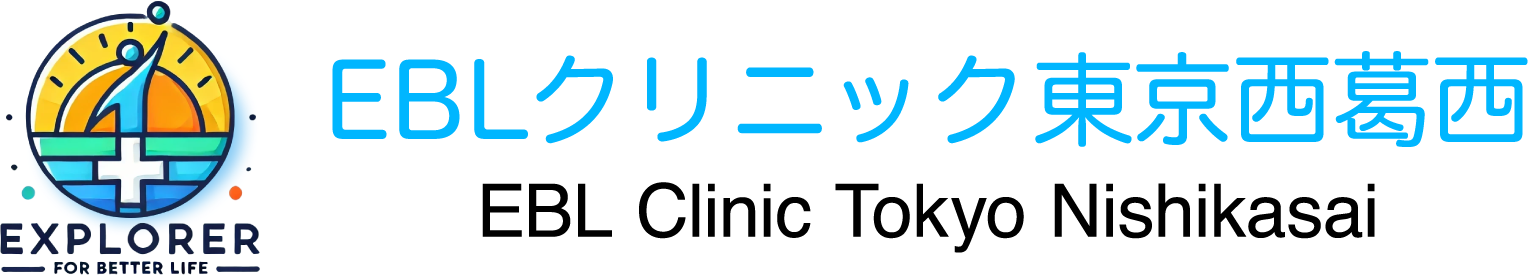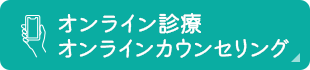うつ病とは
 うつ病とは、気分障害の一種で、気分が落ち込みやすく憂うつになったり、やる気が出ないなどの精神症状と、眠れなかったり疲れやすい、身体がだるいなどの身体症状が現れる病気です。気分障害は大きく「うつ病性障害」と「躁うつ病(双極性障害)」の2つにわけられます。
うつ病とは、気分障害の一種で、気分が落ち込みやすく憂うつになったり、やる気が出ないなどの精神症状と、眠れなかったり疲れやすい、身体がだるいなどの身体症状が現れる病気です。気分障害は大きく「うつ病性障害」と「躁うつ病(双極性障害)」の2つにわけられます。
「憂うつ」「うつ状態」と「うつ病」の違い
憂うつやうつ状態とは、悲しかったりつらかったりなど気分が落ち込んだ状態のことです。憂うつやうつ状態は、日常生活における一般的な感情の変化で、原因が解消されたり、気分転換をしたり、時間が経過することで次第に癒されていくものです。一方、うつ病の場合は、気分が落ち込む明らかな原因が思い当たらなかったり、原因が解消されても気分が回復しない状態です。
うつ病の原因
うつ病の原因は、明らかになっていませんが、何らかの精神的ストレスや身体的ストレスが影響すると考えられています。これは、いじめや失敗、失恋、離婚、死別といった悲しい出来事だけでなく結婚や妊娠、出産、昇進、進学、就職、家の新築、引っ越しなどの喜ばしい出来事でも、環境変化がストレスとなり、うつ病を引き起こすことがあることが知られています。
また、病気や内科治療薬が原因となってうつ状態が生じることもあるため注意が必要です。
うつ状態を引き起こすその他の病気
うつ状態は、うつ病だけでなく躁うつ病(双極性障害)、適応障害、不安障害、統合失調症などの精神疾患や、脳血管障害、認知症、甲状腺機能障害、自己免疫疾患(全身性エリテマトーデス)、消化器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病などの身体疾患が原因で起こることも知られています。他にも、インターフェロンやステロイド剤などの薬の副作用によってうつ状態になることがあります。
うつ病になりやすい人
うつ病は、脳内の神経伝達物質の量だけでなく、うつ病になりやすい性格やうつ病を引き起こすきっかけとなるストレスや環境変化があり、それらが組み合わさることでうつ病になると考えられています。うつ病になりやすい性格は、生真面目、完璧主義、自分に厳しい、凝り性、周りに気を遣うなどが考えられています。
うつ病の症状
うつ病の症状は、気分が落ち込む、物事が楽しめない、常に悪い方に考えてしまう、やる気が出ない、何もしたくない、一日中気分が落ち込んでいる、常にイライラしたり焦ってしまうなどが挙げられます。うつ病になると、物事のとらえ方が否定的になってしまい、自分がダメな人間であると感じてしまったり、普段なら乗り越えられる問題も、実際よりつらく感じてしまうことがあります。また重症になると、死んでしまいたいほどつらい気持ちになることもあります。
周囲の人にもわかるうつ病のサイン
うつ病は、本人が感じる気分の変化だけでなく、周囲から見てわかる変化もあります。周囲の人からみて「いつもと違う」といった以下のような変化を感じた場合は、本人はうつ状態にあるかもしれません。
- 表情が暗くなった
- 自分を責めてばかりいるようになった
- 涙もろくなった
- 反応が遅くなった
- 落ち着きがなくなった
- 飲酒量が増えた
身体に現れるうつ病のサイン
うつ病になると精神症状に気が付く前に、以下のような身体の不調が現れることがあります。
- 食欲がない
- 性欲がない
- 眠れない、過度に寝てしまう
- 身体がだるい、疲れやすい
- 頭痛や肩こりがある
- 動悸
- 胃の不快感
- 便秘、下痢
- めまい
- 口が渇く
心が壊れる前兆は?
心が壊れる前兆として、以下のような症状が現れます。以下のような症状がある場合は早めに受診しましょう。
- 疲れているのに眠れない、寝てもすっきりしない
- アルコールや煙草、消費が増える
- 顔つきが変わる
- 遅刻や欠席が増えるようになる
- 挨拶が出来なくなる
- 表情がなくなる、暗くなる
- 身だしなみが乱れてくる
- ずっとどんよりとしている
- 無理に笑っている
- 自分に対して悲観的になる
- 人とのかかわりを避けるようになる
- 集中できず、ぼーっとする
うつ病の頻度
日本では、100人に約6人が生涯でうつ病を経験するとされています。また、うつ病の患者数は、女性は男性よりも約1.6倍多いことが知られています。女性は妊娠や出産、更年期などライフステージにおける環境の変化が多いため、うつ病の注意が必要になります。
うつ病の検査・診断
うつ病の診断では、一定の診断基準に当てはまるか当てはまらないかといった観点から診断を行っていきます。診断基準には、アメリカ精神医学会が作成した「DSM-5-TR」とWHO(世界保健機関)が作成した「ICD-10」の2つを使用して進めていきます。
うつ病の治療
うつ病の治療には、薬物療法と、カウンセリングを主とする精神療法があります。また、散歩などの軽い有酸素運動を行うことで症状を軽減する運動療法などもあります。
休養を取る
うつ病の治療は、心身の休養を取ることが肝心です。そのためには、職場や学校から離れて自宅で過ごしたり、場合によっては入院するなど、しっかりと休養が取れる環境を整えることが重要です。また、精神的ストレスや身体的ストレスから離れた環境で過ごすことは、その後の再発防止にも効果があります。
薬物療法
うつ病の薬物療法で、主に使用される薬は抗うつ薬です。抗うつ薬は、服用開始直後には効果が現れないため、継続して服用する必要があります。薬の服用は医師の指示に従い、自分の判断で薬の量を増減したり辞めたりしないでください。抗うつ薬のほかに、うつ病による身体症状に応じた薬を処方することもあります。
精神療法
当院では、うつ病で歪んでしまった物事の受け止め方・見方を調整する認知行動療法を行っています。患者様ご自身で自分の考えに「気づき」を得ることで、再発防止や日常生活を過ごしやすくする効果も期待できます。
その他の治療法
その他のうつ病の専門的治療法として、高照度光療法や修正型電気けいれん療法、経頭蓋磁気刺激法などを行うことがあります。必要な場合は、連携する医療機関をご紹介します。
うつ病の人にやってはいけないことは?
うつ病の人に対して避けてもらいたい行動は主に以下の3点です。
特別扱いする
うつ病の人は周囲の視線や言動に敏感で、過度な支えや特別な扱いはかえって、重荷に感じてしまう可能性があります。迷惑をかけてしまっているという思いから、罪悪感を覚え、症状が悪化することもあります。
励ます
うつ病の人に対して「頑張れ!」などと励ましの言葉をかけるのも避けてください。うつ病の人は心が弱っていて、励まされても力を発揮するのが難しい状態にあります。特にまじめな性格の方は、「頑張れと言われたのに頑張れなかった」と期待に応えられなかったことでさらに落ち込み自己嫌悪してしまいます。善意の励ましが、逆にうつ病の人を苦しめてしまうことがあります。
説教する
励ますとは反対に説教をするのも厳禁です。うつ病の人は叱られることで「やっぱり自分はダメなんだ」と自己否定的な考えが強まってしまい、うつ状態が悪化してしまいます。うつ病は心や脳の病気であるため、気合や説教などではなく、適切な治療が必要です。
うつ病の発症から回復まで
うつ病の発症から回復までの過程は、「病初期(急性期)」、「回復期」、「維持期(安定期)」の3つの段階があります。
病初期(急性期)
病初期は、気分の落ち込みや意欲の低下、食欲の低下、睡眠障害などうつ病の症状が最も強く現れている時期です。活動のエネルギーが欠乏している状態であるため、ストレスから離れて、十分に休養を取ることが重要です。また、休養と併せて薬物療法を開始すると約1~3ヵ月ほどで回復傾向になることも多いですが、回復傾向が現れるまでの期間は人によって異なり、半年以上かかる場合もあります。病初期はとにかく休養が重要であるため、ストレスがかからないように過ごしやすい環境を整えることが重要です。
回復期
回復期は、「寝て過ごすのに飽きてきた」「掃除がしたくなってきた」などと、徐々に症状が落ち着き、自然にやりたいことが浮かんでくるようになってくる状態です。回復期は、意欲が回復する一方、調子が良いと思っていた翌日に突然症状が悪化するなど、症状に波が生じる時期であるため、焦ってなんでもやろうとせず、無理せずにできることを段階的に増やしていきましょう。
維持期(安定期)
維持期は、症状が安定してきて、一見治ったかのように感じられますが、まだまだ油断できない時期です。うつ病は一度よくなっても症状が再び現れたり、再発のリスクがあるため、うつ病の症状が回復しても、1~2年は薬物療法を続けて、調子のよい状態を維持しながら、再発予防をしましょう。また、日常生活や社会生活に復帰する中で、うつ病になった原因をもう一度見直し、再発しないように環境を整えたり、周囲の人に話をしておくことも重要です。
高齢者のうつ病
高齢者は年齢を重ねて精神的に安定していると考えられがちですが、体力や気力の衰えや健康への不安、親しい人たちの死別、一人暮らしの孤独感など、環境変化が多く、うつ病になることが多いです。高齢者のうつ病は、身体症状に注目されるあまり、うつ病であることがわかりづらかったり、認知症と間違われてしまうこともあるため注意が必要です。