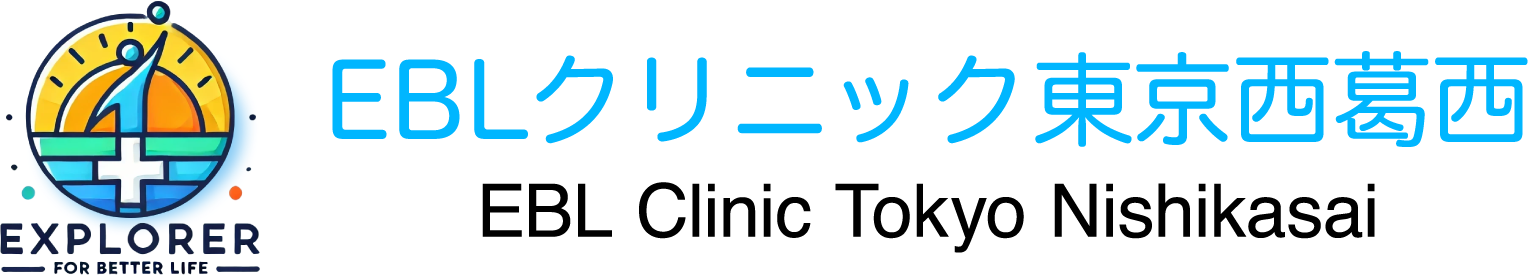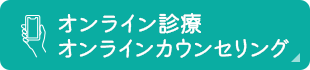更年期障害とは
 更年期障害とは、更年期に起こるホルモンの揺らぎによって、自律神経のバランスが乱れることで、心身に様々な症状が現れ、日常生活に支障が生じる状態のことです。更年期とは、閉経を中心とした前後5年ずつのことを言います。平均的な閉経の年齢は50歳頃であるため、平均的には45~55歳が更年期の年代になります。卵巣から分泌されるホルモンのエストロゲンは、閉経に向かって大きく揺らぎながら減少していき、閉経するとエストロゲンの分泌は止まります。その後、身体は5年程度かけてだんだんと新しいホルモンバランスに慣れていきます。更年期障害はホルモンバランスの変化で起こりますが、生活や仕事、家庭環境なども発症に影響します。症状によっては治療が必要になります。
更年期障害とは、更年期に起こるホルモンの揺らぎによって、自律神経のバランスが乱れることで、心身に様々な症状が現れ、日常生活に支障が生じる状態のことです。更年期とは、閉経を中心とした前後5年ずつのことを言います。平均的な閉経の年齢は50歳頃であるため、平均的には45~55歳が更年期の年代になります。卵巣から分泌されるホルモンのエストロゲンは、閉経に向かって大きく揺らぎながら減少していき、閉経するとエストロゲンの分泌は止まります。その後、身体は5年程度かけてだんだんと新しいホルモンバランスに慣れていきます。更年期障害はホルモンバランスの変化で起こりますが、生活や仕事、家庭環境なども発症に影響します。症状によっては治療が必要になります。
男性も更年期障害になる?
男性も、加齢に伴い男性ホルモンのテストステロンの分泌が減少し、様々な心身症状が起こり、更年期障害と言える状態になります。男性の更年期障害は、女性とは異なり、閉経のような転換点が無いため、症状が何歳までもだらだらと続くことが特徴です。男性の更年期障害は、多くの場合で、自律神経失調症と診断されることが多いです。
若年性更年期障害
若年性更年期障害とは、閉経と無関係に更年期障害のような症状が出る状態です。プチ更年期とも呼ばれていますが、医学的にははっきりとした病態はわかっていません。若年性更年期障害は、閉経に伴う更年期障害とはメカニズムが異なると考えられており、症状は、ストレスや体重減少により、下垂体から黄体形成ホルモン(LH)と卵巣刺激ホルモン(FSH)の分泌が抑制され、卵巣分泌されるエストロゲン(卵巣ホルモン)や排卵後に分泌が増えるプロゲステロン(黄体ホルモン)が十分に分泌されないことが原因で起こると考えられています。
更年期障害の原因
更年期障害の原因は、ホルモンバランスの変化に加えて、壮年期(40~64歳)特有の仕事や子育て、近隣住民との対人関係といったストレス、身体の衰えによる疲労の蓄積などであるとされています。こうした様々な事象にうまく対処しきれなくなると、更年期の身体的変化が重症化して、更年期障害を起こします。
更年期障害の症状
身体症状
- のぼせ、ほてり
- 大汗をかく
- 動悸、息切れ
- 倦怠感
- 疲労感
- 耳鳴り
- しびれ(特に手足)
- 手足などの先端部分の冷え
- めまい、たちくらみ
- 肌・目・口が乾燥する
- 皮膚のかゆみ
- 頭痛、肩こり
- 関節痛
- 腰痛
- 排尿障害
- 月経不順(女性のみ)
- 性欲減退(男性のみ)
- ED(勃起不全・男性のみ)
など
精神症状
- 意味も無くイライラする
- 焦燥感を感じる
- なんとなくいつも不安
- 抑うつ
- 何事にも意欲がなくなる
- 眠れない
など
ホットフラッシュ
 ホットフラッシュとは、更年期障害の代表的な症状で、気温に関わらず急に顔や上半身にほてりが生じ、だらだらと汗をかいたり、のぼせたりするといった症状です。症状は不快である上に、仕事や家事が手につかなくなってしまったり、周囲の人に「暑いですか」と気遣われて負担に感じたりなど、生活や人間関係の支障になることもあります。
ホットフラッシュとは、更年期障害の代表的な症状で、気温に関わらず急に顔や上半身にほてりが生じ、だらだらと汗をかいたり、のぼせたりするといった症状です。症状は不快である上に、仕事や家事が手につかなくなってしまったり、周囲の人に「暑いですか」と気遣われて負担に感じたりなど、生活や人間関係の支障になることもあります。
更年期障害の治療
更年期障害の治療では、一般的に生活習慣や環境の改善と薬物療法を行います。ホットフラッシュについては、女性ホルモン補充療法(HRT)を行い、自律神経症状には主に漢方薬を用います。
薬物療法
更年期障害の諸症状には、漢方薬が有効なものがあります。漢方薬は、病原体や症状の原因に直接作用するのではなく、その人がもっている体質や状態などに合わせて、身体が自然に治ろうとする力を引き出すものです。しかし、精神症状が強い場合は、抗不安薬や抗うつ薬を用いることもあります。
ホルモン補充療法(HRT)
ホルモン補充療法(HRT)とは、更年期に分泌が減少する、エストロゲンやプロゲステロンを薬剤として投与し、更年期の症状を緩和していく治療法です。ホルモン補充療法には、エストロゲンだけを投与する方法や、エストロゲンとプロゲステロンの両方を投与する方法があり、投与方法も錠剤と経皮吸収があるため、患者様の病態に合わせて適切な方法が選択されます。エストロゲンは、乳がんや子宮がんと深いかかわりがあるため、投与前には必ずこれらのがん検診を受ける必要があり、投与中も経過観察として検診を行います。なお、過去にこれらのがんにかかったことがある方や、現在罹患中の方はホルモン補充療法を受けることができません。
生活習慣の改善
更年期障害には、食事、運動、睡眠などの生活習慣の改善が有効です。なお、男性の更年期障害においても、男性ホルモンの低下がみられない場合は、これらの生活改善が有効です。
睡眠、運動の習慣の改善
不眠が続くと、疲労の回復が間に合わず、症状が悪化してしまいます。どうしても寝付けなかったり、夜中に起きてしまう場合は、医師に相談して睡眠薬を処方してもらうのも良いでしょう。運動習慣の改善は、眠りの質を上げるだけでなく、筋力を上げて、更年期の症状に耐えられる身体をつくり、ストレスを解消します。ストレッチやスクワットなど、無理なくできる適度な有酸素運動を習慣化すると良いでしょう。
食事の改善
大豆に多く含まれるイソフラボンは、エストロゲンと同様の働きをするため、更年期の女性は大豆食品を積極的に取ると良いでしょう。また、エストロゲンの低下は、骨粗しょう症を起こしやすくするため、カルシウムや、カルシウムの吸収を助けるビタミンD・ビタミンKを摂取するようにしましょう。男性の場合は、テストステロンの生成を助ける亜鉛を多く含む牡蠣や魚介類、レバーなどを摂取しましょう。またビタミンCは、亜鉛の吸収を良くするため併せて取ると良いでしょう。