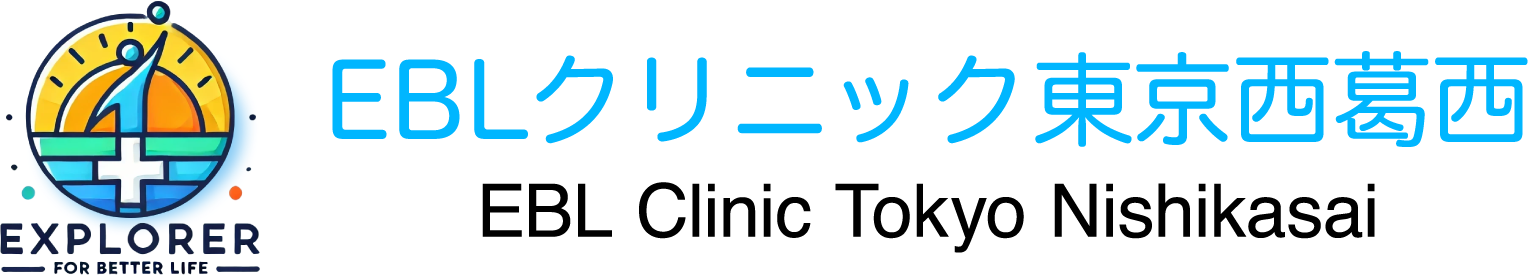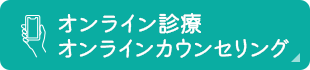生活習慣病とは?
 生活習慣病とは、食事内容や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の影響により、発症する病気の総称で、主に高血圧症や脂質異常症、糖尿病(成人型)、高尿酸血症、心筋梗塞、狭心症、アルコール性肝疾患、がんなどがあります。
生活習慣病とは、食事内容や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の影響により、発症する病気の総称で、主に高血圧症や脂質異常症、糖尿病(成人型)、高尿酸血症、心筋梗塞、狭心症、アルコール性肝疾患、がんなどがあります。
健康診断で数値の異常を
指摘されたことがありますか?
- 健康診断で数値の異常を指摘された
- 血圧が140を超えている
- 20代のときより体重が大きく増えた
- 喫煙する
- 飲酒量(頻度)が多い
- 運動をほとんどしない
- ストレスをよく感じる
- 睡眠時間が足りていない
- 脂っこいものをよく食べる
- 濃い味が好き、塩分を摂りすぎてしまう
- お腹がいっぱいになるまで食べてしまう
など
主な生活習慣病
糖尿病
糖尿病とは、様々な理由によってブドウ糖が細胞内に適切に取り込まれず、血液中のブドウ糖の量が増加してしまう病気です。糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病の2種類があり、2型糖尿病が生活習慣病とされている糖尿病です。2型糖尿病は加齢や遺伝的要因のほかに、過食や肥満、運動不足、ストレスが要因となって発症すると考えられています。糖尿病は進行すると、糖尿病網膜症や糖尿病腎症、糖尿病神経障害など様々な重篤な合併症を引き起こすため、合併症が起こる前に治療を開始することが重要です。2型糖尿病の治療は食生活の見直しと運動習慣を取り入れることから進めていきます。
糖尿病の治療法
糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法の3つを基本として行っていきます。まずは食事や運動による生活習慣の改善を行い、それでも血糖値のコントロールが困難な場合に薬物療法を検討します。糖尿病の治療薬は様々な薬剤が開発されており、インスリンの働きを高めるもの、ブドウ糖の吸収を抑えるもの、余分なブドウ糖を尿から排出させるもの、インスリンの分泌を促すもの、ブドウ糖の利用を高めるものなどがあり、これらは併用していきます。また、インスリンを直接体内に注射することもあります。患者様の病状や生活習慣、検査結果に応じて選択します。なお、過度に血糖値を下げてしまうと、低血糖による副作用が出てしまうことがあるので、薬の選択と量の増減は慎重に検討していきます。
インスリン注射の打ち方
1型糖尿病の治療に用いられるインスリン療法では、インスリンの自己注射が必要となります。当院では、外来にて注射の打ち方や製剤の管理、血糖コントロール、低血糖時の対処などの指導を行っていきます。
メタボリックシンドローム
 メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血圧症、高血糖状態、脂質異常症のうち2つの基準に該当している状態のことです。高血圧症や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、気づかないうちに動脈硬化を進行させ、突然心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを高めます。さらに内臓脂肪型肥満の場合は、動脈硬化が進行しやすく、高血圧症や高血糖状態、脂質異常症に該当しなくても心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。そのため、メタボリックシンドロームの方は、できるだけ早く治療を開始し、適切にコントロールを続けることが重要です。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血圧症、高血糖状態、脂質異常症のうち2つの基準に該当している状態のことです。高血圧症や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、気づかないうちに動脈硬化を進行させ、突然心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを高めます。さらに内臓脂肪型肥満の場合は、動脈硬化が進行しやすく、高血圧症や高血糖状態、脂質異常症に該当しなくても心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。そのため、メタボリックシンドロームの方は、できるだけ早く治療を開始し、適切にコントロールを続けることが重要です。
メタボリックシンドロームの治療法
最も重要なのは、食事内容や運動習慣、睡眠時間などの生活習慣の改善です。ただし、単に食事制限をするだけでは、続けていくのが困難だったり、リバウンドの原因となってしまうことがあるため、ストレスを感じない範囲で楽しみを残しながら治療を勧められるように計画を立てていくことが重要です。
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症とは、高コレステロール血症もしくは高トリグリセリド血症のいずれか、または両方が存在している状態です。また、脂質異常症の中でも、中性脂肪やコレストロールなどの脂質の代謝が阻害され、血液中の脂質成分が正常値を超えている状態を脂質異常症といいます。脂質異常症は、暴飲暴食や偏った食生活、運動不足などの長年の生活習慣が原因で発症する生活習慣病ですが、稀に遺伝により発症することもあります。脂質異常症は無症状のことも多いですが、放置すると動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な病気を引き起こすリスクがあります。
脂質異常症の治療法
脂質異常症の治療方法は、食事療法や運動療法などによる生活習慣の改善から始めます。生活習慣の改善だけでは、効果が不十分な場合は、薬物療法を行います。治療薬には、LDLコレストロールを改善するスタチン系やHDLコレストロールを改善するフィブラート系、中性脂肪を改善するニコチン酸系などがあります。
高尿酸血症
 高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が高い状態が続く病気です。高尿酸血症は、足の指などに激痛を起こす痛風発作を引き起こしますが、痛風発作が起こらないケースもあります。尿路結石や腎機能障害を起こすリスクが高いため、痛風発作が起こらなくても治療は必要です。
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が高い状態が続く病気です。高尿酸血症は、足の指などに激痛を起こす痛風発作を引き起こしますが、痛風発作が起こらないケースもあります。尿路結石や腎機能障害を起こすリスクが高いため、痛風発作が起こらなくても治療は必要です。
高尿酸血症の治療法
高尿酸血症の治療方法は、主にアルコールの摂取制限とプリン体の摂取制限の食事療法による生活習慣の改善に加えて薬物療法を行います。また、一度でも痛風発作を起こしたことがある場合や尿酸値が9mg/dLを超える場合、高血圧症や腎障害、尿路結石、狭心症、糖尿病、メタボリックシンドロームなどの合併症がある場合は、薬物療法を選択します。痛風発作が起きた場合は尿酸値を6mh/dL以下を目標としてコントロールします。一般的に、尿酸の合成を阻害する薬を使用していきます。
高血圧症
 高血圧症とは、血圧が基準値を超えており、慢性的に高い血圧が続いている状態のことです。一般的に健康な成人は、収縮期血圧が135mmHg未満、拡張期血圧が85mmHg未満に保たれており、他に病気がない限りは、これよりわずかに高い血圧が正常とされています。高血圧状態が続くと、血管が硬くなる動脈硬化を起こしやすく、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。ご自宅で計測した収縮期血圧が140mmHgを頻繁に超える場合は、受診することをお勧めします。高血圧症は、少量の内服薬を用いることで、適切な血圧を維持できる場合が多いです。
高血圧症とは、血圧が基準値を超えており、慢性的に高い血圧が続いている状態のことです。一般的に健康な成人は、収縮期血圧が135mmHg未満、拡張期血圧が85mmHg未満に保たれており、他に病気がない限りは、これよりわずかに高い血圧が正常とされています。高血圧状態が続くと、血管が硬くなる動脈硬化を起こしやすく、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。ご自宅で計測した収縮期血圧が140mmHgを頻繁に超える場合は、受診することをお勧めします。高血圧症は、少量の内服薬を用いることで、適切な血圧を維持できる場合が多いです。
高血圧症の治療法
高血圧症の治療方法は、塩分の摂取制限や適度な運動、体重管理、禁煙、禁酒などの生活習慣の改善を行い、それでも血圧が正常値に下がらない場合は、加えて薬物療法を行います。特に日本人は、塩分の過剰摂取をしている場合が多いです。塩分の摂取量は、男性は1日7.5g未満、女性は1日6.5g未満が推奨されています。また、薬物療法に用いられる血圧降下剤は、様々な種類があるため、患者様の状態に応じて、最適な薬を選択したり、必要に応じて複数の薬剤を併用したりします。
肝硬変
肝硬変は、肝臓に起こった炎症を修復するときに生じる線維(コラーゲン)が増加して肝臓全体に広がった状態です。肝臓全体がゴツゴツして硬くなり、大きさも小さくなります。肝硬変は、B型肝炎やC型肝炎、アルコール性脂肪肝炎、非アルコール性脂肪肝炎などの肝臓の炎症によって起こります。肝硬変になると、肝臓が硬いことで、腹水や食道静脈瘤が起こり、肝臓の機能が低下することで、黄疸やこむら返りなどが起こります。
肝硬変の治療法
肝硬変は、肝硬変自体を治療することができないため、肝機能をこれ以上悪化させないための治療を行います。また、肝硬変の治療法は、肝硬変の重症度や原因、年齢、生活環境によって様々です。
脂肪肝
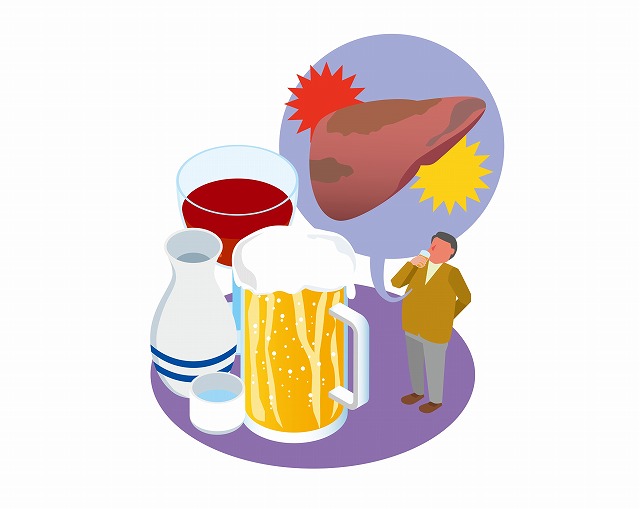 脂肪肝とは、中性脂肪が肝臓に多く溜まった状態(肝細胞全体の30%を脂肪が占める状態)のことです。原因は、過剰な飲酒や肥満、生活習慣病で、アルコールが原因で起こる脂肪肝を「アルコール性脂肪肝」、それ以外の原因で起こる脂肪肝を「非アルコール性脂肪肝」と呼びます。脂質や糖質の摂り過ぎにより、消費しきれなかった脂肪酸やブドウ糖が、中性脂肪として肝臓に蓄えられたり、飲酒により、アルコールを分解する過程で中性脂肪が合成され、肝臓に中性脂肪が溜まります。また、肥満によっても肝臓での脂肪酸の燃焼がされにくくなり、肝臓に中性脂肪が溜まります。さらに、極端なダイエットや食事制限によって低栄養性脂肪肝と呼ばれる脂肪肝になることがあります。
脂肪肝とは、中性脂肪が肝臓に多く溜まった状態(肝細胞全体の30%を脂肪が占める状態)のことです。原因は、過剰な飲酒や肥満、生活習慣病で、アルコールが原因で起こる脂肪肝を「アルコール性脂肪肝」、それ以外の原因で起こる脂肪肝を「非アルコール性脂肪肝」と呼びます。脂質や糖質の摂り過ぎにより、消費しきれなかった脂肪酸やブドウ糖が、中性脂肪として肝臓に蓄えられたり、飲酒により、アルコールを分解する過程で中性脂肪が合成され、肝臓に中性脂肪が溜まります。また、肥満によっても肝臓での脂肪酸の燃焼がされにくくなり、肝臓に中性脂肪が溜まります。さらに、極端なダイエットや食事制限によって低栄養性脂肪肝と呼ばれる脂肪肝になることがあります。
脂肪肝の治療法
脂肪肝の治療法は、食事、運動、禁酒などの生活習慣の改善です。また、脂肪肝を直接治療する薬物療法はありません。肝臓に蓄えられた脂肪は、内臓脂肪や皮下脂肪と比べると減らしやすいですが、一方で脂肪がつくときは肝臓からつくため、生活習慣が元に戻ってしまうと再発しやすいという特徴があります。また再発した脂肪肝はNASH(非アルコール性脂肪肝炎)に進行しやすい傾向があるため、生活習慣を改善し、それを維持することが重要です。
うつ病と生活習慣病
高血圧症とうつ病
高血圧症は心理ストレスと関係が深い病気です。そのため、高血圧症の患者様の中には高い頻度で抑うつ状態が認められることがあります。また、うつ病の人は、普通の人と比べて高血圧症を発症する割合が高いとされています。
うつ病のコントロールで、血圧が安定することがあります
うつ病の治療によって、血圧が安定することがあります。心理ストレスは、脳の交感神経の働きを活発にし、血圧を上昇させます。また、うつ病に多い症状である不眠は、血圧を不安定にさせるほか、抑うつ状態による焦りも血圧を高める要因になります。そのため、高血圧症の治療だけでは血圧のコントロールが不十分な場合に、うつ病の治療を行うことで、血圧がコントロールできるようになることがあります。
糖尿病とうつ病
糖尿病とうつ病には、血糖値や心理ストレスの面から、深い関係があることがわかっており、糖尿病患者はうつ病になりやすく、うつ病の方は糖尿病になりやすいとされています。
糖尿病の合併症などのリスク上昇
うつ病は血糖値のコントロールを難しくするため、糖尿病とうつ病を併発すると、糖尿病の治療効果が下がり、糖尿病神経障害や糖尿病腎症、糖尿病網膜症糖尿病などの合併症が悪化する危険性が高まります。また、それだけでなく、うつ病になると糖尿病の療養行動ができなくなってしまったり、喫煙量や飲酒量が増えるなど、糖尿病の悪化を招く行動を起こしやすくします。