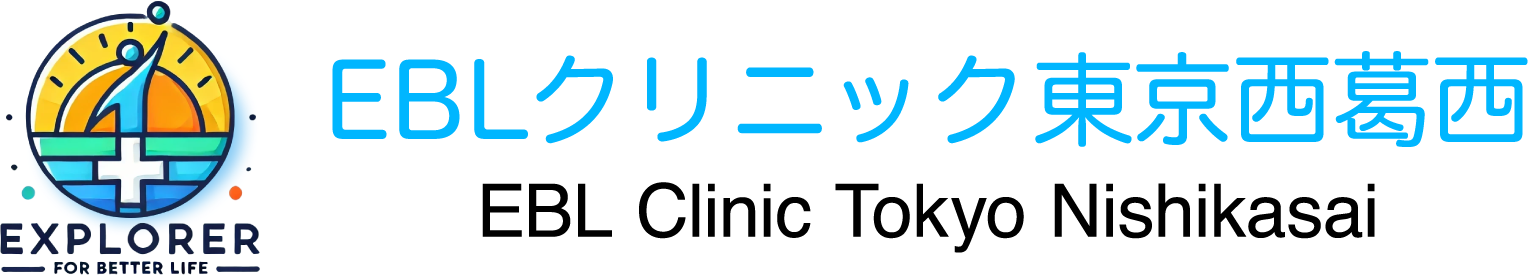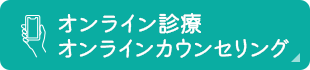過敏性腸症候群
 過敏性腸症候群(IBS)とは、消化器に異常が見つからないのにも関わらず、腹痛や便秘、下痢などのお腹の不調が続き、慢性的に症状を繰り返す病気です。過敏性腸症候群は、腸に炎症や腫瘍などが認められないため、命に関わるような深刻な病気ではありませんが、外出先で突然便意を伴う腹痛が起こったり、便秘による不快感が続いたりと、日常生活に支障をきたし、不安を与えるなど生活の質を下げるような病気です。過敏性腸症候群はストレスとの関係が深いとされており、心身症の1つと考えられています。そのため、ストレスや不安への対策と、食事や生活習慣の改善、お腹の症状の内科的対応などこころと身体の両方から改善を試みていくことが重要です。
過敏性腸症候群(IBS)とは、消化器に異常が見つからないのにも関わらず、腹痛や便秘、下痢などのお腹の不調が続き、慢性的に症状を繰り返す病気です。過敏性腸症候群は、腸に炎症や腫瘍などが認められないため、命に関わるような深刻な病気ではありませんが、外出先で突然便意を伴う腹痛が起こったり、便秘による不快感が続いたりと、日常生活に支障をきたし、不安を与えるなど生活の質を下げるような病気です。過敏性腸症候群はストレスとの関係が深いとされており、心身症の1つと考えられています。そのため、ストレスや不安への対策と、食事や生活習慣の改善、お腹の症状の内科的対応などこころと身体の両方から改善を試みていくことが重要です。
過敏性腸症候群の原因
脳⇔腸の伝達過敏
過敏性腸症候群の原因として、脳と腸の間の神経伝達が過敏になっていることが挙げられます。通常、便が大腸を移動するときには、自律神経の働きによって、腸を収縮させ、便が肛門付近へと到達すると、その刺激が脳に伝わり便意を感じます。しかし、過敏性腸症候群の人はこの脳と腸の間のやり取りが過敏になってしまい、腸からの刺激が大げさに伝わったり、脳が過剰な指令を腸へ返してしまうことで、排便機能に異常を起こします。また、健康な人でも、腸が活発に収縮すると痛みを感じますが、過敏性腸症候群の人は、弱い収縮でも強い痛みを感じやすいと考えられています。
ストレス
過敏性腸症候群は、精神的なストレスによって脳が知覚過敏になることで症状が起こるとされています。腸の消化吸収や排泄は脳の知覚や自律神経の働きによって調整されていますが、過敏性腸症候群の人は脳の知覚が過敏になっていることで、これらの機能の調整がうまくできなくなっています。特に不安や緊張は脳からの腸への信号を過敏にするため、人によっては腸の蠕動運動が過敏になることで下痢になったり、反対に腸が緊張して便秘になってしまう場合があります。また、お腹の症状によって生活が妨げられることでさらに不安を感じたりストレスが高まったりするため、腸の不調が慢性化するという悪循環に陥ることが多くあります。
身体の疲労
過敏性腸症候群は、精神的なストレスのほかにも、疲労などの身体的なストレスの影響を受けます。過労や睡眠不足、運動不足、身体の冷えは腸の働きを悪くし、下痢や便秘を起こしやすくします。
食事
過敏性腸症候群は、食生活の影響を受けます。冷たい物や水分の多いものを取り過ぎたり、香辛料やカフェイン、アルコールなどの刺激物を取ると、腹痛や下痢を起こすことがあります。また、食べ過ぎや、消化に悪い食事は、消化不良を起こし、下痢や腹痛を引き起こします。
細菌・ウイルスの影響
過敏性腸症候群は、ウイルスや細菌による感染性腸炎にかかった後に発症しやすいことが知られています。感染による腸の炎症で、腸の粘膜が弱くなったり、腸内細菌に変化が起こることで腸の知覚過敏や機能異常が起こるのではないかと考えられています。また、特定の細菌によって腸内環境が変化し、過敏性腸症候群になる可能性があることが指摘されています。
体質
過敏性腸症候群は、もともと腸の機能があまり強くなかったり、神経質でストレスを感じやすい人に多いと言われています。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群の主な症状は、便通の異常で、人によって腹痛や下痢、便秘など様々です。過敏性腸症候群には、便通の状態がストレスや環境によって変化するという特徴があります。多くの場合で、自律神経の乱れによる体の症状とこころの症状が合併して現れます。
お腹の症状
- 急な腹痛や便意が頻繁にあり下痢になる
- 緊張やプレッシャーでお腹が痛くなりやすい
- 大切な場面やトイレに行けない場所にいると、お腹が痛くなりやすい
- 外出先で急に便意に襲われ、下痢になることがある
- お腹の痛みは排泄すれば楽になる
- 急な腹痛や下痢への不安によって、外出や大切な用事が怖い
- 下痢と便秘を繰り返す
- 緊張やストレスで便秘になりやすい
- 便秘がちでコロコロとした便が出る
- ガスがたまって苦しい
など
お腹以外の「身体」の症状
- みぞおちが痛む
- 食欲がない
- 頭痛
- めまい
- 動悸
- 尿が近い
- 筋肉痛
- 疲れやすい
など
「こころ」の症状
- 抑うつ状態
- 意欲の低下
- 不安感
- 緊張
- 不眠
- 焦り・イライラ
- 引きこもりがちになる
- 神経過敏
など
過敏性腸症候群とストレス・自律神経
過敏性腸症候群は、こころと体が相互に影響し合って起こる心身症の1つと考えられています。脳と身体は自律神経系で繋がっており、特に腸は脳の影響を受けやすい部位であるとされています(腸脳相関)。また、過敏性腸症候群は、ストレス性の他の障害や、自律神経失調症の症状の1つとして起こることもあり、ストレスや不安でこころが弱ると、身体にも何かしらの変調が起こり、身体が弱るとこころはさらにストレスを感じやすくなります。そのため過敏性腸症候群の根本的な改善のためには、ストレスや生活の見直しなど、自律神経のバランスそのものを整えていくことが重要です。
過敏性腸症候群の治療
過敏性腸症候群の治療では、症状を改善する薬物療法を行いながら、ストレスや食事習慣などの生活習慣改善とリラクゼーション法などを組み合わせて行います。下痢を繰り返すタイプの過敏性腸症候群の方は、不安や緊張を感じやすい人が多いため、お腹の症状の改善のほかに、不安、抑うつの改善の薬を処方することがあります。しかし、薬は過敏性腸症候群を根本的に治せるものではないので、生活習慣改善を行い、心身や生活のバランスを整えていくことが重要です。
機能性ディスペプシア
特別な病気がないのに胃がもたれる、すぐに胃が張ってあまり食べられない、みぞおちが痛む、そのような状態を「機能性ディスペプシア』といいます。ディスペプシアは消化不良の意味で、胃痛や胃もたれなど胃の不快症状を指す医学用語です。機能性ディスペプシアには、ストレスや生活習慣が大きく関わります。人それぞれの状態に合わせた適切な薬を選ぶとともに、ストレスコントロールや生活の見直しなど、「こころ」と「身体」両面からのトータルな治療が根本の改善に繋がります。
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアの直接的な原因は、胃の機能低下・機能障害です。
機能低下・機能障害を招く原因には「こころ」の要素と「身体」の要素があり、人によって複数の原因が関与して発症すると考えられており、ストレス、神経質な性質、食習慣、睡眠不足や過労、カフェインやアルコール、ピロリ菌の関与、体質などが要因として挙げられています。
胃の機能低下を引き起こす原因
上記のような胃の機能低下・異常を引き起こす原因について詳しく説明します。
ストレス
胃はストレスの影響が出やすい代表器官です。悩み事があって胃が痛んだり、ものが食べられなくなったりする人は多いのではないでしょうか。
昔から「ストレス性胃炎」「ストレス性胃潰瘍」などの病名があり、「ストレスで胃に穴があいた」と言われるように、精神的なストレスが胃を弱らせてしまうことはよく知られています。
ストレスは脳を過敏にし、自律神経の働きも乱します。特に不安や緊張やイライラは交感神経を刺激し、消化器官の働きを抑制してしまいます。
そして胃酸の分泌が強まり、胃酸過多となります。
神経質な性質
ストレスというのは人によって感じ方が異なります。大きなストレス要因がなかったとしても、元々神経質で物事に敏感な人や、不安を感じやすい性格の人は日常的に小さなストレスが積み重なりやすく、多くの場合は胃の不快症状を抱えています。
身体の疲れ
ストレスは精神的なものばかりとは限りません。睡眠不足や過労、暑さ・寒さなど身体的な負担も胃の機能を低下させます。
食習慣
胃の機能低下には食習慣が大きく関与します。元来自分が持っている胃の機能をオーバーする過食、消化の悪い高脂肪食や高カロリーな糖質の摂り過ぎ、刺激の強い食べ物、冷たいものをよく食べるなどの状態があると胃が弱りやすくなります。
カフェイン・アルコール・喫煙
過度なアルコールやカフェインの摂り過ぎも機能性ディスペプシアの原因の1つになります。過度のアルコールは胃酸の分泌を強めます。カフェインは胃の刺激となるばかりではなく、脳を刺激し不安や緊張を高める原因にもなります。
喫煙は胃の血液量を低下させ、活動力を弱めてしまうことがあります。
薬の影響(痛み止めの常用など)
普段常用している薬の副作用によって胃腸障害が起こることがあります。特に痛み止め・解熱剤としてよく使用されるNSAIDs(非ステロイド抗炎症薬)のなかには胃を荒らしやすいものが多いため、常用している人は注意が必要です。
体質
体格や体力が人によって違うように、内臓にも生まれ持った機能の強弱があります。元来痩せ型で胃の小さい人や、胃の消化機能が低い人はストレスや疲労の影響も受けやすくなります。
ピロリ菌感染
ピロリ菌は、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・慢性胃炎・胃がんなどの病気と関与の深い、胃粘膜に住み着く細菌です。慢性胃炎の多くはピロリ菌感染によるものと考えられています。
機能性ディスペプシア自体との関連性は定かになっていませんが、慢性胃炎とともにピロリ菌感染が確認されたときは除菌療法を行い、除菌後も自覚症状がなくならないときに機能性ディスペプシアとして治療を行います。
感染性胃腸炎
激しい嘔吐や下痢を症状とするサルモネラ菌など感染性胃腸炎にかかった後は、胃の機能が低下します。症状が重く期間が長引いたときは胃腸の機能がなかなか回復せず、機能性ディスペプシアの原因になることがあります。
機能性ディスペプシアの症状
症状は人によって様々ですが、以下のようなものがあります。
- 食後に胃がもたれる
- 少量食べるだけでお腹が張る
- 胃の圧迫感がある
- ムカムカする
- よく吐き気がする
- みぞおちのあたりがいつも痛む
- 胸焼けがする
- 吐き気がする
- げっぷが多い
など
機能性ディスペプシアとストレス・自律神経
機能性ディスペプシアの原因には様々なものが関与すると考えられていますが、一番大きいのはやはり「ストレス」と「生活習慣」です。
人の内臓はストレスによって様々な影響を受けます。脳と内臓は自律神経系・内分泌(ホルモン)系・免疫系を介して密接に繋がり、お互いに影響を及ぼしあって作用しているため、「こころ」に不調があれば「身体」もつらくなり、「身体」に症状があれば、「こころ」もつらくなります。
また、睡眠、食事、運動、などの生活習慣のリズムは、自律神経のバランスに大きく関わります。
「身体」に不快な症状があれば、身体に何か原因があるのだろうと考えるのが普通ですが、実際には、ストレスや生活習慣の積み重ねが主な原因となって「身体」に影響しているケースも多いです。
機能性ディスペプシアでは胃を中心に不快症状が起こっていますが、ストレスや生活習慣によって自律神経のバランスが乱れれば、全身の様々な部位に影響が起こります。特に不安や緊張などで交感神経が過度になると、
- 胃腸の消化活動が抑制される
- 唾液の分泌が減少する
- インスリンの分泌が低下する
など、消化にかかわる全体の流れが悪くなってしまいます。
機能性ディスペプシアの治療
機能性ディスペプシアの治療ではストレスや生活習慣の見直しが欠かせません。とはいえ、それらの改善には時間がかかります。患者様は現在の不快症状によってつらい状態にあり、その症状自体がストレスとなってさらに状態がつらくなる悪循環を起こしていることが多いため、つらい症状に対しては適切な薬を組み合わせていきます。
薬によって症状を和らげながら、ストレスについて整理したり、不安や緊張を感じやすい状態へ心理的なアプローチをしたり、生活習慣を整えていくことを地道に積み重ね、自分の「こころ」や「身体」と上手に付き合っていける状態を目指します。
機能性ディスペプシアは、薬で完治させられる「病気」ではありません。日々のストレスとの付き合い方や、生活習慣、元来の性質、体質などが組み合わさった結果の「胃の機能低下」です。
根本的な改善のためには、日ごろから自分にかかっているストレスを振り返るようにしたり、睡眠・食事・運動などの習慣に注意するなどのことを継続的に行っていくことが大切です。それらの積み重ねは機能性ディスペプシアの改善だけではなく、様々なストレス性障害や生活習慣病を予防することにも繋がります。