- 慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)とは
- 慢性疲労症候群の原因
- 慢性疲労症候群になりやすい人の特徴
- 慢性疲労症候群の症状(慢性疲労症候群のセルフチェック)
- 普通の疲れとの違いとは?慢性疲労症候群の診断基準
- 慢性疲労症候群の治療
慢性疲労症候群
(筋痛性脳脊髄炎)とは
 慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)とは、明らかな原因がないのにもかかわらず、身体が動かせないなど、日常生活に支障が出るほどの重度の倦怠感や疲労感が6ヵ月以上、長期間にわたって続く病気です。CFS (Chronic Fatigue Syndrome)とも呼ばれます。慢性疲労症候群は、風邪や気管支喘息などをきっかけとして、発症することが多く、休んでも疲れが回復しなかったり、摂食障害や不眠などを伴っている場合は注意が必要です。該当する症状があり、全身の検査(血液、ホルモン、内臓、脳、神経系の検査)を行っても異常が見つからない場合に慢性疲労症候群を疑います。
慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)とは、明らかな原因がないのにもかかわらず、身体が動かせないなど、日常生活に支障が出るほどの重度の倦怠感や疲労感が6ヵ月以上、長期間にわたって続く病気です。CFS (Chronic Fatigue Syndrome)とも呼ばれます。慢性疲労症候群は、風邪や気管支喘息などをきっかけとして、発症することが多く、休んでも疲れが回復しなかったり、摂食障害や不眠などを伴っている場合は注意が必要です。該当する症状があり、全身の検査(血液、ホルモン、内臓、脳、神経系の検査)を行っても異常が見つからない場合に慢性疲労症候群を疑います。
慢性疲労症候群の原因
 慢性疲労症候群は原因や病態が明らかになっていませんが、様々な研究の結果、ストレスがきっかけとなって神経系の働きに異常が起こり、免疫の働きが低下することで、体内に潜伏したウイルスが再活性化されると考えられています。また、その再活性化したウイルスを抑え込むために作り出された過剰な免疫物質が原因で、脳の働きに影響を及ぼし、強い疲労感が生じると考えられています。ある特定の遺伝子に関する異常も関連するとされています。
慢性疲労症候群は原因や病態が明らかになっていませんが、様々な研究の結果、ストレスがきっかけとなって神経系の働きに異常が起こり、免疫の働きが低下することで、体内に潜伏したウイルスが再活性化されると考えられています。また、その再活性化したウイルスを抑え込むために作り出された過剰な免疫物質が原因で、脳の働きに影響を及ぼし、強い疲労感が生じると考えられています。ある特定の遺伝子に関する異常も関連するとされています。
慢性疲労症候群に
なりやすい人の特徴
- 表現力が豊かな人、明るく温かみのある人
- 従順で協調性が高い人、周囲の期待に応えようと努力する人
慢性疲労症候群の症状
(慢性疲労症候群の
セルフチェック)
- 微熱がある
- 頭痛がある、頭が重いと感じる
- 喉の痛みがある
- 疲労感がある
- 筋肉痛がある
- よく眠れない、または寝すぎてしまう
- 気分障害
普通の疲れとの違いとは?
慢性疲労症候群の診断基準
多くの場合、疲れは、良質な睡眠やバランスの取れた食事などの十分な休養を取ることで回復しますが、慢性疲労症候群では、十分な休養をとっても回復しません。慢性疲労症候群の診断基準は以下の通りです。3つの中核症状すべてに該当し、2つの追加症状の少なくとも1つを満たす場合に、慢性疲労症候群と診断されます。
中核症状
- 大幅な活動レベルの低下:仕事や学業などの社会生活や日常生活において、発症前よりも活動レベルが著しく低下した状態が6ヵ月以上にわたって続く
- 労作後倦怠感(PEM):軽い労作後やストレスの後に、12~48時間後に強い倦怠感が出る(数日または数週間続く)
- 睡眠で疲れが取れない:通常通り睡眠をとっているのにもかかわらず、疲れが取れず、気分がすぐれない
追加症状
- 認知機能障害:言葉を記憶したり、物事に注意を向けたり、何か物事を行うことが困難
- 起立性調節障害:立ちくらみや湿疹、疲労、認知力の低下、頭痛、吐き気などがある
慢性疲労症候群の治療
慢性疲労症候群の治療では、漢方を中心とした薬物療法を行います。主に捕中益気湯という漢方薬を用いて、身体の免疫力を高めます。また、活性酸素による細胞の障害を防ぐために、抗酸化作用をもつビタミンCを大量に服用したり、抗ウイルス薬や免疫調整剤を用いて免疫系の回復を図ります。また、抗うつ剤や精神安定剤などを用いることもあります。内科治療の効果が見られない場合は、ストレスに対処するための方法を探すことを目的としたカウンセリングも行います。
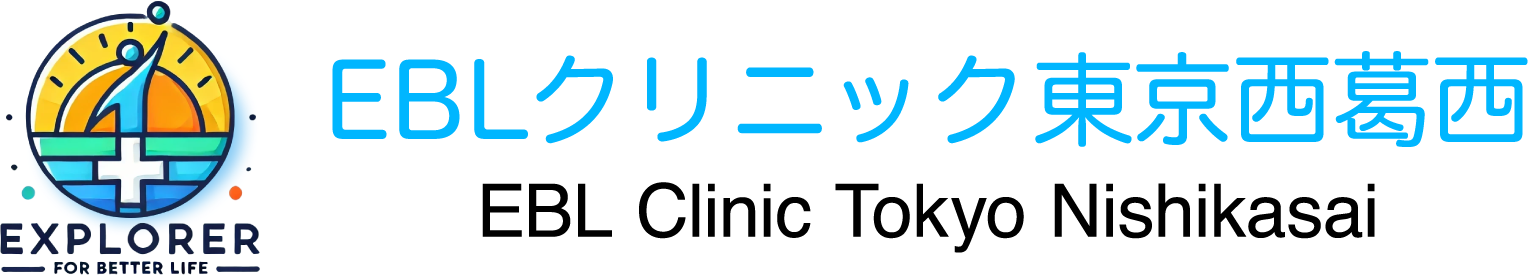








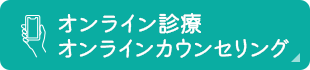

 慢性疲労症候群は、鍼灸治療で自律神経やホルモンバランスを整えることで、改善することがあります。
慢性疲労症候群は、鍼灸治療で自律神経やホルモンバランスを整えることで、改善することがあります。